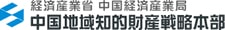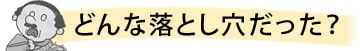- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 著作権で保護できる範囲の落とし穴
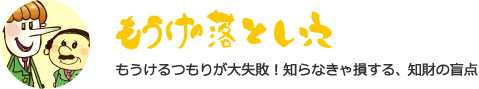
著作権で保護できる範囲の落とし穴
デザイン性に優れている製品。その製品を保護するのに著作権で守るの?
それとも意匠権で守るの?<平成28年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
A社は、新商品を開発した。新商品はデザインに特徴があるので、A社の社長は、デザインといえば美術の分野であり著作権法で保護されると考えた。著作権は登録しなくても権利が発生するとのことだったので、そのまま販売を開始した。しばらくして、他社から似たようなデザインの商品が販売されたので、著作権に基づいて警告しようと専門家に相談した。すると、A社の商品は、デザインに特徴があるといっても、いわゆる工業デザインであって本来意匠法で保護されるものであり、著作権法で保護されるものかどうか微妙であると言われてしまった。