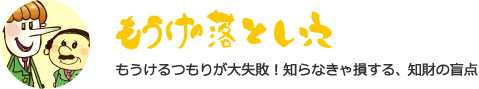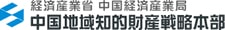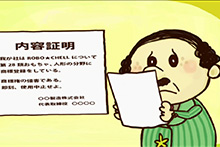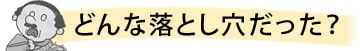特許の要件の一つに新規性があります(特許法第29条第1項)。特許制度は、発明の公開の代償として独占権を付与するものですので、既に公開されて公に知られている発明に対して独占権を付与する必要はなく、また付与すべきではないからです。ここで注意しなければならないのは、既に他人が同一の発明を公開していた場合だけでなく、自身が発明した新製品の展示会への出展、メディアへの露出、販売行為等により公開した場合にも新規性を喪失してしまう点です。できるなら、新製品の評判を確かめてから、必要に応じて特許を出願したいところですが、それはできません。従って、新製品を公開するにあたっては、公開前に特許出願を完了しておく必要があります。なお、新規性の判断基準時は出願時ですので、特許出願完了後であれば、特許付与前であっても公開により新規性を喪失することはありません。
また、展示会への出展、メディアへの露出、販売行為等とまではいかなくても、新製品に関する発明の内容を取引先に話して反応を見るケースがありますが、その場合には、その取引先との間に秘密保持義務が生ずるかどうかについて十分留意しなければなりません。秘密保持義務は必ずしも書面による契約を必要とするものではなく、東京高裁平成12年12月25日判決は、開発がらみの引き合いにおける当事者間の社会通念上又は商慣習上の秘密保持義務を認めていますが、個別の事案毎に判断されるものですので、できるだけ書面により明らかにしておくことが望ましいといえます。
一方、特許法には新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。これは、公開した発明であっても、定められた例外期間内に定められた手続きに則って特許出願すれば、新規性を喪失したことにならないというものです。
しかしながら、あくまでその公開により新規性を喪失したことにならないというだけであって、出願日自体を遡らせることはできません。そのため、自身の公開から特許出願までの間に、他人が自ら発明して先に特許出願したり公開したりした場合には、特許を受けることはできませんので、例外規定を利用する場合であっても、できるだけ早く出願する必要があります。また、新規性喪失の例外規定の有無や内容は国によって異なりますので、外国出願を検討している場合にも注意が必要です。

信末 孝之
弁理士
三原・信末特許事務所
特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。