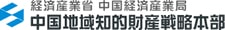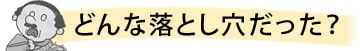- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 改良した周辺特許を取らない時の落とし穴
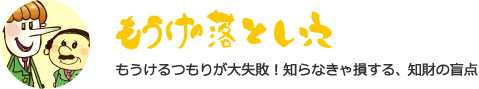
改良した周辺特許を取らない時の落とし穴
新製品の開発に成功した社長!さらに、追加機能でどんどんパワーアップする構想まで!まずは、完成した新製品の基本特許のみを取得した。同時に追加機能の開発もスタート。2年が過ぎ追加機能の開発も順調に進んだのだが・・・<平成24年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
A社は新製品の開発に成功し、開発した新製品について特許出願することとなった。この新製品には、今後様々な機能を追加していく予定であり、その内容もほぼ確定しつつあったが、現在実物として完成している製品は、基本的な機能のみを有するものであったので、その実物が有する基本的な機能のみについて特許出願した。その後無事に特許権を取得することができたものの、当初から予定していた追加機能については、競合他社が先に特許出願してしまい、特許権を取得されてしまった。