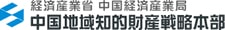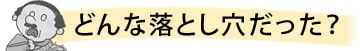- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 共同出願特許の効力範囲の落とし穴
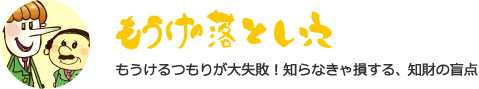
共同出願特許の効力範囲の落とし穴
有名企業A社と共同で、特殊な商品を開発した製造会社B。特許も共同で出願した。B社が製造販売して数ヶ月、製造ラインを持たないA社が、下請けに安く作らせ販売。 え?そんなこと勝手にしてもいいの??<平成21年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
大きな企業と一緒に技術開発を行い、特許を共同で出願した。その際に、特段の契約は結んでいなかったが、相手方である大企業は、特許製品の製造ラインを持っていなかったので、当方の製品を大企業へOEM供給できると期待していた。しかし、大企業の方では、下請会社で安価大量に製品を製造させ、当方の製品は市場でも全く売れなくなってしまった。