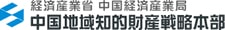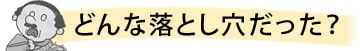- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 自社技術を客観的に見ていない時の落とし穴
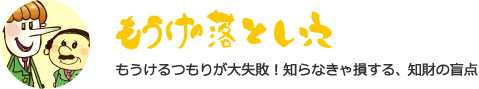
自社技術を客観的に見ていない時の落とし穴
自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ,他社から特許権を侵害しているから,その技術を使ってはいけないとの警告が来た。独自技術開発したのにそんな話っておかしいでしょ~。その証明を見せてみろ~だって。一体どういうこと~。<平成23年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
新しい技術開発に成功したが、既存技術の改良であって、特に開発に苦労したとも感じなかったので、「こんなものは特許にならないだろう」と判断し、特許出願しなかった。しばらくして、その新しい技術を適用した製品の製造販売を開始した。ところが、他社から当該製品の製造販売が特許権侵害であるとの警告を受けてしまった。調べてみると、他社でも同じ時期に同じ技術開発に成功し、当社が製造販売を開始する前に特許出願していた。