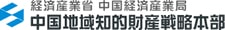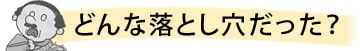- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 実用新案の権利を主張する時の落とし穴
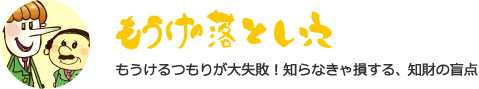
実用新案の権利を主張する時の落とし穴
実用新案を取得し、満を持して発売した画期的な製品。ライバル企業から模倣品が出たって「実用新案権」さえあればダイジョウブ♪なはずが・・・、「実用新案技術評価書」って何? 「権利の有効性が無効」って何~<平成20年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
自社で新たに開発した製品A。実用新案登録出願を行って「実用新案権」も取得し、製品Aの売上げは順調に伸びていきますが、ライバル企業が模倣品を販売し始めます。この模倣品は、自社の実用新案権の権利範囲に抵触すると考え、ライバル企業に警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談。すると、実用新案権の権利行使のためには、「実用新案技術評価書」を提示して警告することが必要であるとのこと。特許庁に対して、実用新案技術評価を請求し、返ってきた「実用新案技術評価書」の内容は、「権利の有効性について否定的」なものであり愕然とします。このまま警告を行うと、むしろ実用新案登録が無効にされて、逆に損害賠償を請求される恐れがあることから、警告を断念することに・・・。