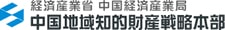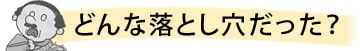- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 模倣品への特許侵害警告の落とし穴
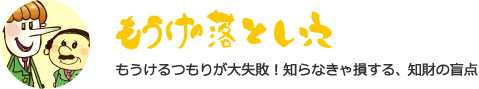
模倣品への特許侵害警告の落とし穴
自社の特許を侵害されたと気付いたある会社。この模倣品を買わないようにと自社の顧客に文書を配布。しかしよく調べると、模倣品は特許侵害ではなかったため、逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けた!<平成20年度制作>
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
ある特許権を有する会社が、「ライバル企業が模倣品を販売しはじめた」との情報を得ます。
直ちに自社の顧客へ『自社特許を侵害するライバル企業の模倣品を購入しないように!』との文書を配布しますが、実際には特許権を侵害するものではなかった・・・・。しかも逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けてしまって・・・。
さあ、どうなる???