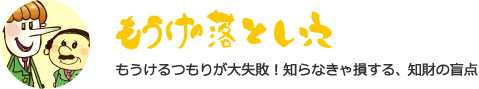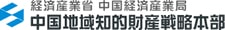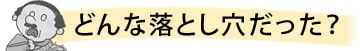発明が行われた場合,その発明に係る権利は,当該発明を行ったものに帰属するものとされています。従業員の行った職務発明についても,原則的には発明を行った従業員に権利が帰属することとなります。ところで,平成27年に改正される前の法律では,特許を受ける権利は実際に発明を行った従業者等が有し,これを契約や勤務規則等によって使用者等が承継した場合には,相当の対価の支払を行うこととなっていました。しかし,相当の対価が不合理でないものでなければならなかったところ,その不合理性の判断基準が不明確であり,予測可能性が低いこと,従業員から特許受ける権利の譲渡を受ける場合,二重譲渡がなされた場合や,共有にかかる場合に,問題が生じること等の指摘があり,法改正に至りました。
平成27年改正後の特許法では,「従業員等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。」(法35条3項)こととされました。すなわち,発明が完成した時点で,通常は従業員等に帰属する特許を受ける権利が,最初から使用者等に帰属することができるようになり,その結果譲渡ではないため二重譲渡の問題は発生せず,また共有の場合も相手方の承諾なく権利を取得することができることとなりました。
しかし,そのためには,「あらかじめ」,すなわち発明の完成の前までに,定めをしなければなりません。これは契約でも可能ですし,その契約は口頭でも,場合によっては黙示の合意でも可能であると解されていますが,通常は明確にするため,職務発明規程等を作成するべきです。さらに前記のとおり,相当の対価が平成27年の法改正により相当の利益に変更となり,そのガイドラインも制定されておりますので,相当の利益を与える旨を定めたうえで,当該規程を従業員に開示する必要があります。
こうした定めをすることにより,特許を受ける権利を使用者等に原始的に帰属させることが可能となりますが,使用者等がこうした定めを置いていない場合は,従業員等が特許を受ける権利を取得することになります。もっともその場合でも,使用者等には法定の通常実施権が与えられることになっていますので,特許を受ける権利の帰属についてどう対処するかについては,経営戦略をたてたうえで検討する必要があると考えられます。

山本 英雄
弁護士
加藤・山本法律事務所
昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。
企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。