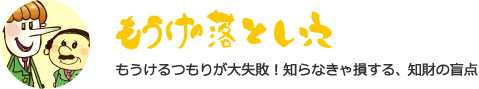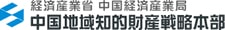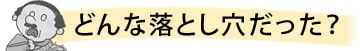一つの企業だけでは得意分野や経営資源に限りがあるため、他の企業や大学等と新技術、新商品の共同開発を行うケースが多くなっています。
動画にもあるように、共同開発を行う際には「書面による契約」が重要です。
まずは、情報漏えいの危険を考慮し、共同開発に関する契約について交渉を行うスタート段階で秘密保持契約(NDA)を結ぶ必要があります。なぜなら、交渉の段階で開示される情報自体(開発の目的、対象商品など)が重要な秘密情報だからです。
次に、共同開発に関する契約を結ぶ際には、まず目的を「具体的に」定めること、言い換えれば、ゴールと成果物が、明確にイメージできるように記載されていることが重要です。そして、開発期間も明確に定めておきましょう。
さらに、開発の役割分担、費用負担、進行状況・成果の報告、成果の知的財産権の取扱い、知的財産権取得の手続き、秘密保持義務なども規定します。
たとえば、A社(メーカー)とB社(販売会社)で共同開発をして、その成果物である新商品Xに関する特許権を共有したとします。「パートナーのB社から受注を受け、Xを製造するのは、当然わが社だ」と、A社が信じていても、別段の契約がなければ、B社は、A社の同意を得ないで、C社(A社ではない他のメーカー)に製造委託することも出来ます。
共同開発契約は、他の一般的な契約に比べて、複数の契約が含まれ、内容もひじょうに複雑なため、契約書の作成には、経験や専門知識が必要です。
したがって、初めて共同開発を行うときには、契約に関し、各都道府県の知財総合支援窓口や、専門家(知財に詳しい弁護士など)の具体的助言を受けることをお薦めします。
筆者は、日常的に中小企業を訪問しています。その際に、産学連携(大学や公的研究機関との共同開発)を行っているケースで、成果として得られた「秘密として守るべき」最重要な技術ノウハウが、企業側の知らないところで大学や公的研究機関などによって研究会等で公開されてしまっているのを、ときどき見かけます。
成果を特許等で権利化する場合、あるいは営業秘密として秘匿化する場合、いずれにおいても厳重な秘密管理が必須で、相手の自由な裁量で発表されない様な「契約による縛り」も必要です。

小原荘平
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)
知的財産戦略アドバイザー
家電メーカーに34年間勤務。研究開発部門で約20年、法務・知的財産部門で約10年、精密電子部品の開発、事業化、ライセンス渉外業務などを行う。日本機械輸出組合知的財産権問題専門委員会委員も務めた。