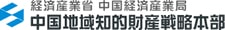- もうけの花道トップページ
- もうけの羅針盤
- 顧客との関係性にイノベーションを起こす!前編
~創業180年 江戸時代から続く老舗仏具店がカフェをOPEN~
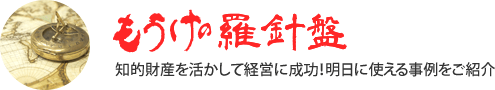
顧客との関係性にイノベーションを起こす!前編~創業180年 江戸時代から続く老舗仏具店がカフェをOPEN~
江戸時代から続く老舗の仏具店。時代と共に家庭の仏壇離れが進み、業界の売り上げはここ20年でおよそ半分に…
限界を感じていた仏具店が新たな営業スタイルとして打ち出したのは、オシャレなカフェ!?一見ミスマッチに見えるカフェの営業だが、顧客とのコミニケーションにイノベーションを起こし仏具の売り上げもアップ!そのきっかけとなったのが、経営デザインシートだった。後編はこちら
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
「ぬしや仏具店」とは
江戸時代、嘉永年間創業。漆塗りと金箔をなりわいとし、昭和30年代より漆器・雑貨などの小売り店舗を開業。昭和51年、仏壇の小売業を本格化。
塗師屋(ぬりしや)が転じて「ぬしや」と呼ばれるようになり、その屋号が店舗名となった。
仏壇離れで営業が悪化。江戸時代から続く老舗仏具店がカフェをオープン!?顧客との関係にイノベーションを起こす!
江戸時代、嘉永年間創業の老舗仏具店「ぬしや」。次期6代目となる現在の営業部長の将人さんとその妻 志帆子さんは世の中の仏壇離れに危機感を感じていた。
実際に業界の売り上げは、20年でおよそ半分。亡くなった人がいて始めて営業ができる仏具店ならではの営業スタイルにも限界を感じていました。
その打開策として2人が考えたのが職人技術の付加価値を高める位牌のブランディング。
地元の商工会を通し相談を持ちかけました。すると商工会はブランディングの実績をもつ中小企業診断士の五島さんを岡野夫妻に紹介。しかし、頼む機会が少ない上に単価が数千円程度という位牌のブランディングに五島さんは疑問を感じ別の糸口を探すことに…
そこでまず岡野夫妻に勧めたのが「経営デザインシート」の記入。金銭的な現状打開の戦略ではなく、経営理念と今後のあるべき姿を構想するための思考補助ツールでした。
岡野夫妻が話しあい、シートに記載した答えが「たくさんのお客さんに来て欲しい」、「職人の技術を身近に見て欲しい」、「スタッフ皆が笑顔でいられる職場でありたい」という経営の悪化から心の奥底に隠していた“本当の気持ち”。
そんな経営デザインシートを見て中小企業診断士の五島さんが提案したのは、なんと“カフェの営業”。
想いもよらぬ提案に驚いた岡野夫妻だったが、カフェのOPENに向けて、大きな一歩を踏み出したのだった。