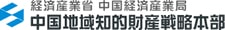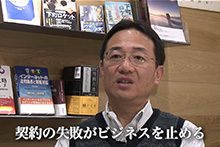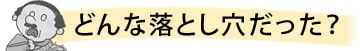- もうけの花道トップページ
- もうけの落とし穴
- 共同研究における契約トラブル
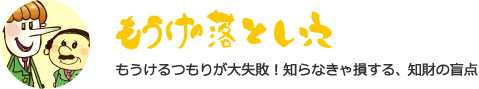
共同研究における契約トラブル
大企業と中小企業が共同研究を行うことになった。共同研究が始まる前に、契約書を交わすこととなったが、中小企業にとって、共同研究の権利の帰属は、納得できない内容だった。〈令和3年度作成〉
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
大企業A社(アグリマシナリー)は、中小企業S社(沢田電研開発)の保有する革新的な蓄電技術を自社の農機具に実装したいと希望し、共同開発を打診した。A社の法務担当から共同開発にかかる契約内容の説明を受けたS社の社長は、開発成果の帰属に疑問を感じつつも、A社との関係構築を重視するあまり、その場で契約書に署名をしてしまった。結果として、共同開発の成果はすべてA社に帰属することになり、S社は大切なノウハウを無償で提供してA社の新製品の立ち上げに協力しただけに終わった。