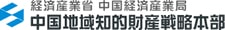- もうけの花道トップページ
- もうけの羅針盤
- 借入過多の会社の未来と金融機関の新発見~資金調達編~
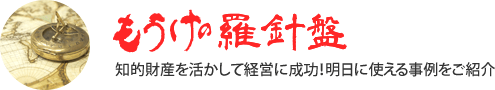
借入過多の会社の未来と金融機関の新発見~資金調達編~
メッキ加工が使われる移動体通信の拡大に伴い業績が右肩上がりの時代、特殊鍍金化工所は大きな設備投資を行っていた。しかし、様々な事業環境の変化の中で業績は一転。その困難を切り抜けるために活用した経営デザインシートによって、金融機関のバックアップを引き出すことに成功した。〈令和3年度作成〉
動画をブログで紹介する
上記コードをはりつけてください
- ※
- お使いのサービスによっては、正常に表示されない場合もあります
セミナーアーカイブ
もうけの花道動画を活用して行った経営者・中小企業支援者・支援機関・金融機関向けに開催したセミナーアーカイブです。
- ・借入過多の会社の未来と金融機関の新発見 ~資金調達篇~
この事例の企業は
株式会社 特殊鍍金化工所
東京都三鷹市井口3-15-8
http://www.tmk.co.jp/japanese/com_pro/index.html![]() 0422-31-2313
0422-31-2313
![]() 代表取締役 柴 太
代表取締役 柴 太
技術力で創業30年間、右肩上がりの受注から極めて厳しい状況に。
1963年の創業以来、貴金属へのメッキ処理、主に国内通信機器メーカー向けにコネクターなどのメッキ処理加工を行ってきた。創業から30年は右肩上がりで受注も伸び、ポケットベル携帯電話など移動体通信事業に関連するメッキ加工は、会社の業績を安定させる業務になっていた。しかし2000年以降、原材料の価格高騰、環境問題への規制などさまざまな問題に直面し厳しい状況に。クライアントの要求や過剰な設備投資が追い打ちをかけ、気が付けば借入金は、年商の倍にまで達し、資金調達余力は極めて限定的な事態が続いていた。
金融機関の信頼を勝ち取る
経営コンサルティングのマネジメントパートナーズによる経営改善への取り組みにより、芝社長が初めて取り組んだのが【経営デザインシート】。
これまで、金融機関を含めて様々なところから事業計画を作りなさい。と言われて取り組んできた柴社長。しかし、どれも現状の業務の延長線上で考えないと、どこも認めてくれない。というアドバイスばかりだった。
マネジメントパートナーズの清水さんは、そんな考え方では会社をもっとよくしたい、もっと大きくしたいということに繋がらない。思いきって明るい未来にチャレンジしてほしい。
ということで、経営デザインシートの取り組みを始めた。
柴社長は、経営者である自分だけではなく、従業員と一緒に取り組むことが重要。
また、その取り組みにメインバンクである多摩信用金庫も参加してもらい、経営デザインシートの作成を行った。その結果、メインバンクの多摩信用金庫から高い評価を得て、融資の長期対応や短期継続融資などを実現したのです。
経営デザインシートとローカルベンチマークを活用
経営デザインシートで将来像を描こうとするも、なかなか思いつかない。ローカルベンチマークを活用することで、自社の強みやシーズの洗い出しで現状認識でき、自社技術の可能性を発掘することに成功。これまでとは違った分野への挑戦へとつながった。
柴社長は、世の中が5年10年で変わっていく中で、今、出来た経営デザインシートをベースに、よりきちんと見直してその時代に合ったアップデートをして先へ進んでいきたい。と語ってくれた。