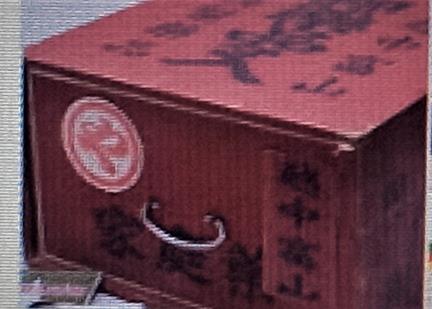昆布にまつわる話の数々
2023年8月1日
中山勝矢
今年の中国地域ニュービジネス協議会(CNBC)は、6月6日に総会と表彰式を岡山駅に近いホテルグランヴィア岡山で行いました。
総会に引続き、大賞1件、優秀賞4件、特別賞6件が表彰されました。これらはいずれもCNBC会長賞ですが、大賞には例年同様、中国経済産業局長賞も授与されました。(写真1)
表彰の際に記念写真の撮影があり、さらにその後に受賞者が受賞の内容について講演をします。会場には受賞者の展示ブースもあり、参会者にとっては優れた勉強の機会です。
人々の知恵の塊
さて昆布の話を始める前に、産地に触れておきましょう。私たちが馴染んできた昆布は、古くから北海道産で、その多くは保存のため、日干しにしてありました。(写真1)
日本の人が昆布を知ったのは、紀元前219年、中国の徐福(じょふく)という人が秦の始皇帝に願い、多数の供を連れて不老不死の薬を求めて来日したときからだとされます。
すでに漢方には天台烏薬(てんだいうやく)の根から採る中風に効果がある薬が知られていました。徐福は高血圧予防やがんの免疫強化の薬として昆布に着目したのです。
彼は富山を中心に各地で水産業や農業を教えたようで、西日本には20か所余りも徐福の伝説が残っています。さらに東か北に船を向けたようですが、その後の消息は不明です。
わが国で食卓に昆布やわかめなどが並ぶようになるのは、6世紀の仏教伝来に伴い導入された精進料理に関係があります。海藻で精進料理の味を整えたのでしょう。
当時昆布の産地である北海道は外地でした。原住民であるアイヌ民族の蝦夷(えみし)が海藻を採り、日に干して自家用を蓄えていたものと思われます。
万葉集には海藻を読み込んだ歌が100首ほどあるそうですが昆布はなく、主題はアラメやワカメだといいます。わが国は、今日でも世界で海藻をよく食べる国なのです。(写真2)
当時わが国の勢力範囲は、日本海側は越後まで、太平洋側はおおよそ関東平野の手前までで、荘園から集める租税の中には海藻もあったようです。
7世紀斉明天皇の時代まで盛んに武力で攻めましたが、その後半に越後の国守になった阿倍比羅夫が方針を改め、蝦夷の産物である乾燥昆布の納入も認めることにしたようです。
はじめ輸送は陸路でしたが次第に海路が増え、越前の富山を経て京に運ばれました。船は北前船と呼ばれ、大型となる一方、港の神社には安全を祈る絵馬が多数残されています。
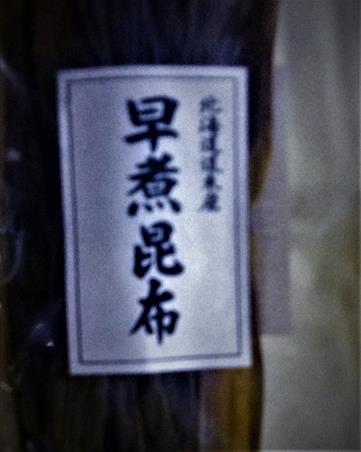

人々の知恵の塊
全国で一人当たりの昆布消費量のトップは、富山県なのです。古くから流通の拠点だったのですから、当然と言えば当然だと理解できます。
ところが第2位が、何と沖縄県那覇市であるのには驚きました。上位10位までを並べた表を見せられた時、理由が思いつかず、首を傾げてしまったことでした。
富山といえば置き薬の商いが有名です。荷を担ぎ、全国の客の家を訪ね、置き薬用の箱を前に、使用量の確認と清算とを行い、次の置き薬の種類と量を決めていきます。(写真3)
北海道から入手した昆布とその加工品も、この置き薬方式のネットワークを活用して紹介され、全国津々浦々まで運ばれたのでしょう。
この富山の薬屋さんは、いつも棒状に作られた昆布の菓子をお土産に持参し、お愛想に客の家の子どもに配っていました。それが欲しくて、母の傍に座ってじっと待ったものです。
江戸時代はまだ鎖国の時代ですから、本州、四国、九州では海外貿易はご法度です。沖縄(当時は琉球)は薩摩藩の属国でしたから、持ち込まれた昆布は中国貿易に密かに使われました。
そしてその結果は莫大な利を生み、薩摩藩は内緒でその利を溜め込んだのです。これが薩摩藩の財政立て直しと、明治維新に際して軍資金になったという説明には、目が開かれました。
昔も今も、沖縄県は昆布の産地ではありません。北海道こそが水産資源の一大産地なのです。長い時代の中で、売り方から、保存法、食べ方まで工夫を重ねた方々に感謝したいものです。
そうして経済における市場の開拓と流通の課題に目を向け、時代が変わる予兆を前向きに捉えて、過去から未来へ飛躍しようではありませんか。