あいさつ言葉に新年を考える
2023年1月4日
中山勝矢
明けましておめでとうございます 。
新年最初の3日間 、また年初からの1週間は松の内で正月だとして、このような挨拶が交わされています 。
さてこの挨拶の言葉ですが、誰しもが使うのによく分からない点があります。どうして最初が「明けまして」、続いて「おめでとう」なのか構わずに、広く使われてきました 。
すべての言語を調べたのではありませんが、例えば英語圏で「新年おめでとう」は「Happy New Year」です。これは素直で、分かり易い挨拶文です。(写真1)
このように社会に定着してしまっている言葉は、来歴不明で意味不明瞭でも議論を始める人はいません。時代の変わり目と言われるのですから、少し考えてみたくなりました。
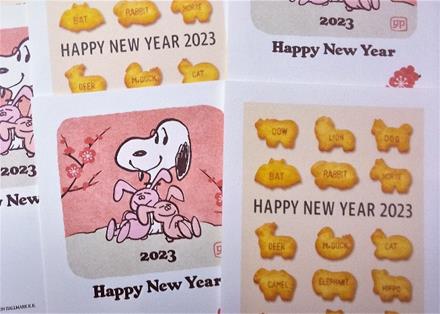
元旦の日の出
日が昇って一日が始まるのは、南北両極の地域を除けば、どこでも同じはずです。それなのに1月1日だけを元旦と呼び、特別扱いにする理由はどこにあるのでしょうか。
元旦の「元」は1月1日に限らず最初を意味します。そうして「旦」の下部にある横イチは地平線あるいは水平線で、その上に太陽を置いて元旦と呼び、1月1日を指します。
このように1年の初日を、新しい一年が始まる特別の日として、それに続く一年が幸いに富み、災いのない一年であるように願うのは誰も同じです。
仮に地平線、あるいは水平線から現れた太陽が異常な姿だったら、人々は不安に陥ります。だから「常々と変わらない姿で太陽が上がりました、おめでとう」なのでしょう。
12月中旬に、元旦の日の出を題材に1月号の原稿に着手しましたが、天候の予想がつかず困り、仕方なく古い写真をイメージとして使いました。ご容赦ください。(写真2)

「明けまして」の来歴
わが国の「おめでとう」には「明けまして」が先行しています。朝明けるのは当たり前と考えていた若い頃は、なぜ正月だけ夜が明けると目出たいのか分かりませんでした。
多分、訊ねられたらみな困るのではありませんか。誰も、教えてくれないし、テレビや新聞雑誌で解説を見た覚えもありません。昔からこうなのだと突き放されるのがオチです。
歴史を紐解くと、数百年前から商工業が盛んになり、江戸時代後期には貨幣経済の浸透とともに、帳付けしておき、月末に支払うのが普通になった様子が書いてあります。
大晦日は一年の終わりですから、深夜まで催促と集金に飛び回り、算盤片手に勘定を帳簿に記したことでしょう。深夜に仕事を終え、年越しの夜食は多分、夜鳴きそばでした。
一年の間には水害も日照りもあり、地震や台風による災害もあって貸し倒れも出ました。「明けまして」は、決算の夜を何とか切り抜けた同輩への慰労と祝福の言葉なのです。
一年間の苦労をこなして迎えた新しい年への夢と期待を励まし合う言葉でもあるのでしょう。そうした気持ちが「明けましておめでとう」から感じ取れませんか。
先行する「明けまして」で、古い年の厄払いを終え、新しい年こそはと願う想いを重ねてゆき、年頭の挨拶にまでしたのは見事で、社会に広く定着したのだと思われます。
太陽に願う気持ち
ところで初日にそれほど関心がない人でも、元旦の太陽には心が動くようです。1年1回の初日の太陽を見るために、多くの人がわざわざ海岸や丘の上まで出かけて行きます。
目の前が大きく広がり、遠い地平線、あるいは水平線から太陽が顔を出し始め、周囲が次第に明るさを増すとその偉大さに圧倒され、誰しも思わず手を合わせてしまうのです。
今日では、巨大な太陽は水素から成り、内部では核融合反応で莫大なエネルギーが生み出されているというのが常識です。その誕生は約50億年前とされても、寿命は不明です。
この太陽が放出する光を含む放射線により、地球上では、様々な気象現象や生命連鎖が生じています。つまり人を含むすべての生物に対して食料と環境を提供しているわけです。
地下資源である石炭、石油も元は植物です。言い方を変えれば、太陽の活動が休止すれば、地球上の環境は激変し、あらゆる生命体は食糧を失い、残るのは死のみです。(写真3)
特別な宗教心がない人でも、太陽がなくなれば地球上の生命が消滅するくらいのことは知っています。その恐れと元旦の太陽に圧倒され、自然と手を合わすのでしょう。
